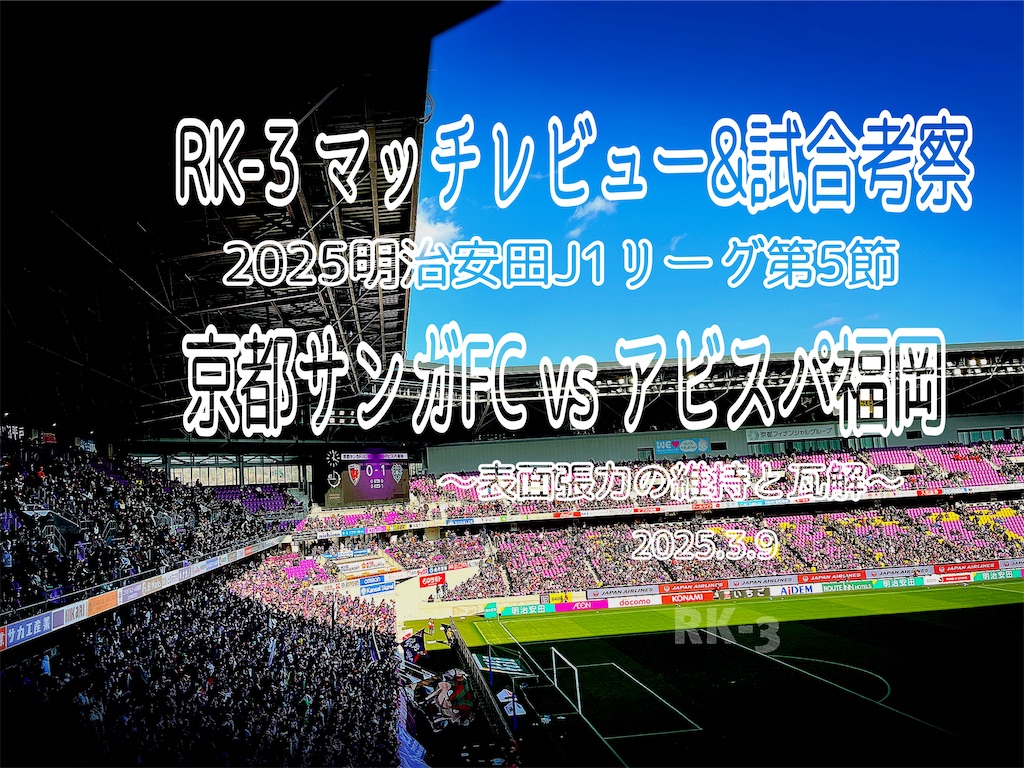
伝統の一戦って呼んでいます
どーもこんばんは
さてさて、本日のマッチレビューは2025明治安田J1リーグ第5節、京都サンガFC vs アビスパ福岡の一戦です!
【Jリーグをもっと楽しめる(かもしれない)、2025Jリーグ開幕ガイド作りました!是非お使いくださいませ!】
↓
【オリジナルアルバム出してみました!聴いてみてくださいませ!】
↓
思えばお互いよくここまで来たもんだ、とでも言いましょうか。
1993年から始まったJリーグには、いわゆるオリジナル10と呼ばれる1期生がいて、その後に1996年までに2チームずつが増えていきました。図らずも、いわば4期生としてJリーグに同期入会を果たしたチーム、それが京都サンガとアビスパ福岡でした。
昨季30周年を迎えたサンガと今年30周年を迎えたサンガ。その成り立ちに違いはあっても、福岡の経営危機が深刻化した時期を除けばJリーグで立っていた境遇はどこか似ていたように思います。J2という概念が生まれれば主戦場はいつの間にかJ2に移り、J1とJ2を行き来する生活が訪れた。その中でサンガはJ2生活が主でも5年に一度はJ1に上がれる福岡を羨みましたし、福岡側から見てもJ2から抜け出せなくてもなんやかんやで星を持ち経営基盤を持っている京都への羨望は少なからずあったような気がします。
2025年、今の福岡は欠けていた星を掴み、今の京都はJ1に舞い戻ってきた。お互い、J1の舞台を自分達の居場所とするべく邁進する日々の中に今日の一戦はあります。共に前節初勝利を果たしたチーム同士、30シーズン目の邂逅の結末やいかに。
両チームスタメンです。


サンガは初勝利を挙げた前節川崎戦からのメンバー変更は1人のみ。川崎戦はジョアン・ペドロを先発に起用しましたが今日は川﨑颯太に戻しており、マルコ・トゥーリオの負傷に伴い原大智の右WG起用も継続。ベンチメンバー20名のくくりでは1人だけ変更があり、今日はク・ソンユンではなく圍謙太郎が第2節浦和戦以来のベンチ入りとなりました。
対する福岡は4バックで開幕した後3バックに変更しましたが、今日はスタートは4バックに戻しており、初勝利を挙げた神戸戦からは先発を2人変更。出場停止の上島拓巳の代わりに志知孝明が左SBに入り、CBは田代雅也と安藤智哉のコンビ。ワントップはシャハブ・ザヘディが今季初先発となりました。古巣対決の湯澤聖人はスタメン、岩崎悠人はベンチスタートです。
本日の会場は京都府亀岡市、サンガスタジアム by Kyoceraです。
今日の試合ではゲストとして、普段からプライベートでサンガ戦に足繁く通う森脇健児氏が来場。スタジアム場外を含めると3度にわたってトークショーが実施される予定です。本日は前回のホームゲームでホームゲーム通算入場者数450万人を突破した記念のステッカーが配布される他、抽選でスタグルとグッズのクーポンが当たるチャンスも。また、今季より復活した西京極時代の施策「フレンズ広場」では当時人気を博していたお子様用スライダーが再登場するそうで。あと森保一監督も来ているそうで。
思えば2020年、サンガスタジアムにとって初の有観客の公式戦の相手は長谷部茂利監督体制4試合目だったアビスパ福岡でした。思い出も因縁も詰め込んだスタジアムで行われる日曜唯一の試合です。
現地観戦でした!段々春日和になりまして。スポーツ観戦日記はまた。
というわけで来ました。#京都サンガ#アビスパ福岡 pic.twitter.com/6e1Nks9MIn
— RK-3 (@blueblack_gblue) 2025年3月9日
試合は序盤から福岡ペースでした。
開始5分に左サイドに流れてボールを受けたザヘディが持ち込んでミドルを放ったところに始まり、直後にも藤本一輝から見木友哉に渡ったボールをポケットで受けた紺野和也がシュートに持ち込みますが、ここはGK太田岳志のセーブでなんとか阻止。
基本的にサンガはハイラインを設定する事で連続して連動したハイプレスを繰り出せるような陣形を組み、その連動の上にハーフコートゲームに近い陣形を組む事を目指して試合に入る事が基本スタイルですが、この日はザヘディを最前線に置いた福岡がそこへのロングボールを起点にラインを押し上げるタイミングを作り、そこからハイラインを設定してプレスを繰り出す…ある意味でサンガやりたい事に近い陣形を福岡に組まれる形になり、試合としては受け身にならざるを得ない時間が続いていきます。
それゆえに浦和戦や川崎戦で見せた良い時のサンガらしい高い位置でのボール奪取からのショートカウンターを繰り出せるような機会は殆どありませんでしたが、ある程度構えながらサイドで1対2の状況を作って局地的なハイプレスを仕掛けて攻撃に転じられるような場面もあり、ミドルプレス的にプレッシングの出力具合を調整しながらチャンスに繋げる流れは得意な展開でないなりにも生み出す事はできていました。
11分にはルーズボールを拾った福岡慎平のパスを受けた平戸太貴がミドル、24分には右サイドを突破したエリアスの折り返しに奥川雅也が反転からシュートまで持ち込みますが、いずれもGK村上昌謙のビッグセーブに阻まれます。
39分には平戸が放った直接FKが壁に当たってドライブ気味になったところをまたしてもGK村上がビッグセーブ。逆に福岡は41分にゴール前の混戦から最後は紺野が決定機を迎えますが、今度はGK太田がビッグセーブ。
苦労人なキャリアを歩んできた両GKがJ1で見せる圧巻のパフォーマンスが光る前半となりましたが、試合を優勢に運んだのは明らかに福岡。一方のサンガは悪い展開なりの立ち振る舞いを見せ、0-0のまま後半に向かいます。
福岡は後半からメンバーは変えずにシステムを3バックにシフト。志知を3バックに組み込み、藤本をWBに置きつつ紺野と北島祐二を2シャドーに配置します。
後半も福岡が主導権を握りました。後半開始から1分にも満たない場面で左サイドを突破すると、北島の折り返しに中に入っていた藤本が混戦からシュート。これはサイドネットに救われましたが、前半は4-2-3-1でサンガに対してマンツーマン的にプレスで追い込みやすいシステムだったのを、今度はより前線で生じるズレを福岡が有効活用しやすい形になっていきました。
福岡は62分にザヘディと負傷退場となった湯澤を下げてウェリントンと前嶋洋太を投入。64分には福岡がGK村上からパスワークを開始すると、そこから面白いようにワンタッチ、ツータッチのパスをテンポ良く繋がれて気が付けば藤本が一気に左サイドを打開。そこからの福岡の波状攻撃はGK太田の好セーブもあって阻みますが、瓦解の足音が聞こえる展開に。
迎えた65分、敵陣にボールが入ったフェーズでサンガはラインを上げようとしますが、相手のクリアボールに反応したウェリントンにそのままラインをひっくり返される状況を献上すると、佐藤と競り合ってウェリントンがボールを残し、それを拾った紺野が巧みなステップワークからニアを射抜くミドルシュート。これが決まって福岡が先制。サンガにとっては開幕戦以来のビハインドに。
切り返しから左足一閃#ウェリントン の強さから#紺野和也 相手の逆をつく巧みな先制ゴール🔥
— DAZN Japan (@DAZN_JPN) 2025年3月9日
🏆明治安田J1リーグ第5節
🆚京都×福岡
📺#DAZN 配信中 #京都福岡 pic.twitter.com/GXa2qMGY4p
失点直後の67分にサンガは川﨑を下げてペドロ、ウェリントン対策か宮本を下げてパトリック・ウィリアムを投入。73分には奥川と平戸を下げて平賀大空と中野瑠馬を送り込んで回転数を増やそうと試みると、78分には原を下げて長沢駿を投入して反撃機会を伺います。
しかしハイプレスの前に中盤ではボールが絶望的に落ち着かず、時折左サイドにポイントを作って切り込もうとするような瞬間こそありましたが、そこからのパスは出し手・受け手共に尽くズレてしまい、危険を与えられるようなエリアにほとんど侵入できないまま福岡にサイドから旋回するようなカウンターを受け続ける状況を強いられていました。
アディショナルタイム、ラストプレーではペドロの斜めからのクロスボールにエリアスがやや遠い位置からヘディングで合わせますが…シュートは僅かに枠の外。
前半は保てていたバランスは福岡のプレスの前に時間経過と共に崩れ去り、苦しい内容と結果での敗北を喫しました。
今季は岡山戦だけはマッチレビューを書けていないのですが、勝ちゲームだった、或いは実際に勝てた浦和戦・神戸戦・川崎戦と大筋では同じような書き方になっていると思います。というのも、曺貴裁京都は良くも悪くも勝因と敗因が近いところにある、わかりやすく表裏一体的な部分があるのが特徴と言えて、内容は勝ち試合を演じた浦和戦も実際に勝った川崎戦も、そして負け試合をちゃんと負けた福岡戦も根底にあるものは同じ…という事です。大前提として一概にそれを否定するつもりは無いですし、肯定的に捉えられる部分もありますが。
サッカーの戦術を少し齧るようになると「再現性」なる言葉はよく聞くフレーズで、その対義として「出たとこ勝負」「ギャンブル的なー…」みたいな批判が寄せられる事がままある訳ですが、基本的にサンガがの勝ちゲームの内容になるか負けゲームの内容になるかは「序盤からサンガ優位のゲーム設定を作れるかどうか」「サンガのペースに相手を付き合わせられるかどうか」で、逆にこれが出来なければ負けゲームの内容になる。前者は浦和戦が明確でしたし、川崎戦は必ずしもサンガ優位の試合では無くとも川崎をサンガのペースに付き合わせる事が出来たのは確かでした。内容は必ずしも上の要件に準じていないものもありましたが、去年のサンガは上位2チームと降格3チームとの対戦成績が全て1勝1敗だったように、サンガにとってはその試合を「勝てる設定のゲームに持ち込めるかどうか」が全てですので、上に対しても下に対しても実力差と戦力差が結果と内容に比例しない…試合が始まるまでどちらの展開になるかわからない…という意味では実にギャンブル的なチームでありながら、勝ち試合の設定にさえ持ち込めば良い内容のゲームをできるという部分では再現性を持っているチームとも言えるんですね。
BS中継のような多くの他サポが見る試合で良い内容のゲームを見せた時に普段サンガを追ってまでは見ていない人から「あれ?もしかして京都結構強い?」的な声がそこそこ聞こえてくる割には、一部のサンガファンはいつものパターンだと冷めた目を見せていたりするような、そういう内外の評価のギャップが生まれる要因の一つはサンガの持つ性質にあるように思います。
で、話を福岡戦に戻すと……今日は明確にサンガが勝てる設定の試合にならなかったゲームであり、むしろサンガがやりたいようなハイライン・ハイプレスを福岡にやられる形になってしまい、サンガにとってこの試合は完全に「不利な試合の設定」という状況になってしまいました。
福岡としては上述したサンガの性質を踏まえて、如何にサンガのゲームにならないようにするか…という手当てをしっかり実践してきた。例えばサンガは原大智にロングボールを入れる事で原が最終ラインを押し込み、平戸や川﨑が原からボールを受ける時にはハーフコートゲームを組み立てられるような状況になっている、原にボールを当てる事で純粋なポストプレーとプッシュアップの時間稼ぎを両立させるという狙いがあった訳ですが、福岡はフィジカルでタメを張れる安藤智哉を原に当てる、或いは原とてジャンプしながらボールをキープする事は出来ない訳で競り合う人と拾う人の2人がかりで原を潰しにくるといった具合にサンガの起点を徹底的に潰してきた事で、サンガがラインを押し上げる時間を得られないような守り方をしてきました。
加えて、おそらく福岡はベン・カリファがいない以上はプレスへの貢献を優先させるならウェリントン、相手を押し下げる事を優先させるならザヘディみたいな使い分けがあってその後者を選択してきた訳ですが、ここがサンガとしては結構苦しかった。見方によってはサンガのハイラインにザヘディが引っかかりまくってオフサイドが多かった…という側面もあったんですが、個人的にはむしろ逆で、ザヘディがオフサイド上等の構えをされてしまった事でサンガの守備陣が牽制されてしまっていた部分はあったのかなと。サンガの攻撃時には左WBのようなポジションを取って関与しながらも背後にスピード勝負をされた時のCBのカバー役も兼ねる佐藤が、時間経過と共に3バックの左のようなポジションにならざるを得なかったのはそこの影響もあったように見えました。
ただ、そういう不利な設定の試合になってしまった時のサンガは大概何も出来ないまま散っていく事が多かったこれまでと比較すると、不利な設定の試合に追い込まれてしまったらしまったで、悪い時なりの立ち振る舞いはある程度できるようになった…という感想は前半は抱ける内容ではあったように思います。サンガにとっての悪い試合というのは「シンプルにボコボコにされた/自滅でボコボコにされた試合」と「序盤からサンガの得意な陣形を作れず、不利な設定に持ち込まれた試合」の2つがあって、前者ならもうどうしようもないですが、後者ならその中での立ち振る舞い次第では勝ち筋余地がある…前半はその勝ち筋はなんとか保てていたんですね。
昨季後半は平戸や福岡、トゥーリオの起用でボール保持時の攻撃ビジョンをある程度持てるようになったところがV字回復に繋がりましたが、今季は神戸戦でも顕著だったように場面に応じてミドルプレスに移行する時間帯、プレスの出力を段階的に調整するような取り組みは見せていると思います。その点ではこの試合はまずサンガのやりたいようなハイラインとハイプレスは福岡に封じられる形になってしまったという前提があった中で、昨季ならそれでもハイプレスで行こうとして引っくり返されがちになっていましたが、今日は悪い状況になった事を受け入れてある程度割り切って守る姿勢を見せていましたし、ハイプレスを繰り出すタイミングを局地的なものに限定する事でセーフティーにやろうとする意図は統一されていた。そこで昨季前半のように無理にチャレンジして大崩れするような場面は少なくとも前半はあまり無かったですし、そこの押し引きが出来るようになったのは昨季と比べた時にチームとしてやれる事が増えた部分ではあったと思います。ここは今季は特に佐藤と須貝のところでサイドの対人守備が機能している自身の表れもあるでしょうし。ボールを持った際にも下手にアタック、アタック、アタック…となる場面を抑えながら、平戸や福岡のゲームメイク、原の起点となる動きを使ったカウンターを狙う意識を持っていた事で決定機もいくつか訪れた訳ですし。
ただ、福岡がハイラインとハイプレスを基軸に前線でボールを動かそうとしてきた前半はそれで凌げたんですが、後半から3バックに変更してSBとCBの間のポケットを狙うやり方にシフトしてくると、サンガの守備者の距離感がそこからバグるようになってきたというか……福岡も攻撃開始のポイントを一列下げてきた事で、サンガのラインを引っ張り出される形になってしまった。この時のハイラインは最初からやろうとしたものではなく無意識的に引き摺り出されたものでしたし、その割には前半の割り切った意識も中途半端に残ってしまっていたので、特に失点前後の場面は「ハイラインだけどハイプレスに行かない」という状況に陥ってしまっていた…と。後半の福岡は紺野や北島が常にそのギャップを突いてきた事で蹂躙状態になってしまったのはサンガにとって痛恨でした。1点を取られてからそれまでどうにか維持していた秩序を手放す形になってしまったのはこのクラブの悪癖ですし、それは岡山戦でも露呈したポイント。今日は前半は悪いなりの立ち振る舞いが出来ていたからこそより顕著に移ったところなあるかなと。
あと前も言ったけど長沢はイメージの割にパワープレー向きのFWじゃなくて、クロスボールも空中戦に強いんじゃなくて反応に秀でたタイプだから、エリアスを残して原を下げた以上はあのスタンスで別に間違ってない。… https://t.co/18QwZwzvka
— RK-3 (@blueblack_gblue) 2025年3月9日
付け加えて言うと、この日の交代策に関しては…議論の対象になっている「なぜ長沢を入れてパワープレーしないの?」という点に対しては、別にあの使い方で間違っていないと考えています。
上に貼った投稿のように、長沢は190cmを超える身長のイメージから山﨑凌吾やパトリック的な使い方がイメージされますが、長沢は実は空中戦にさほど強い選手ではなく、パワープレーで長沢に放り込んで競り勝つ…みたいなプレーが得意な選手では無いです。むしろ動き出しや線を点で合わせるワンタッチゴーラー的な動きに強みを持つ選手なので、原ではなくエリアスを下げて長沢を入れた時点で空中戦ではなく地上戦を選択した事自体は間違ってなかったと考えています。曺監督としても、おそらく安藤や田代のいる福岡守備陣との空中戦勝負はそこに至るまでの展開を踏まえても分が悪い…という考えだったと思いますし、それまでに投入したのが平賀や中野だった事で一応の整合性は取れているのかなと。
ただ、それなら平戸を残しておくとかそういうアプローチは必要だったと思いますし、逆に今一つ精度を欠いていたエリアスを下げて原を残してパワープレーに振り切った方が良かったと思う点もある。チームとしても監督としても、これまではやられるだけだった状況を取り繕えるくらいの対応策は見せていたので、そこを見ればチームとしてやれる事は増えた。ただ時間の経過と状況の変化と共に一つずつ剥がれていき、采配も含めて一つずつズレとしてピッチに表れていった…終盤のパスミスの連続はそういう意味で皮肉な光景ではありましたね…。
結果的にこの試合は、まず間違いなく完敗ではありながらも、サンガとして苦手な展開なりに勝ち筋を残す戦い方は途中までは出来ていた。でもそれも時間経過と共に瓦解した。現体制を否定的に捉えるあまり粗探し的に試合を見る人にとっては素材の多いゲームであり、逆に肯定的に捉えている人にとっては特徴的なアグレッシブさに欠ける淡白なパフォーマンスに映るという、なんというかまあ全員にとって大きなフラストレーションを募らせるゲームだった……悪いというよりも重いゲームでしたね。
【うれしはずかしじゅんいひょうのコーナー】
2025明治安田J1リーグ第5節分はガンバ大阪vs清水エスパルスのマッチレビューページに記載しています。
この日は鯖寿司食べてました
ではでは(´∀`)