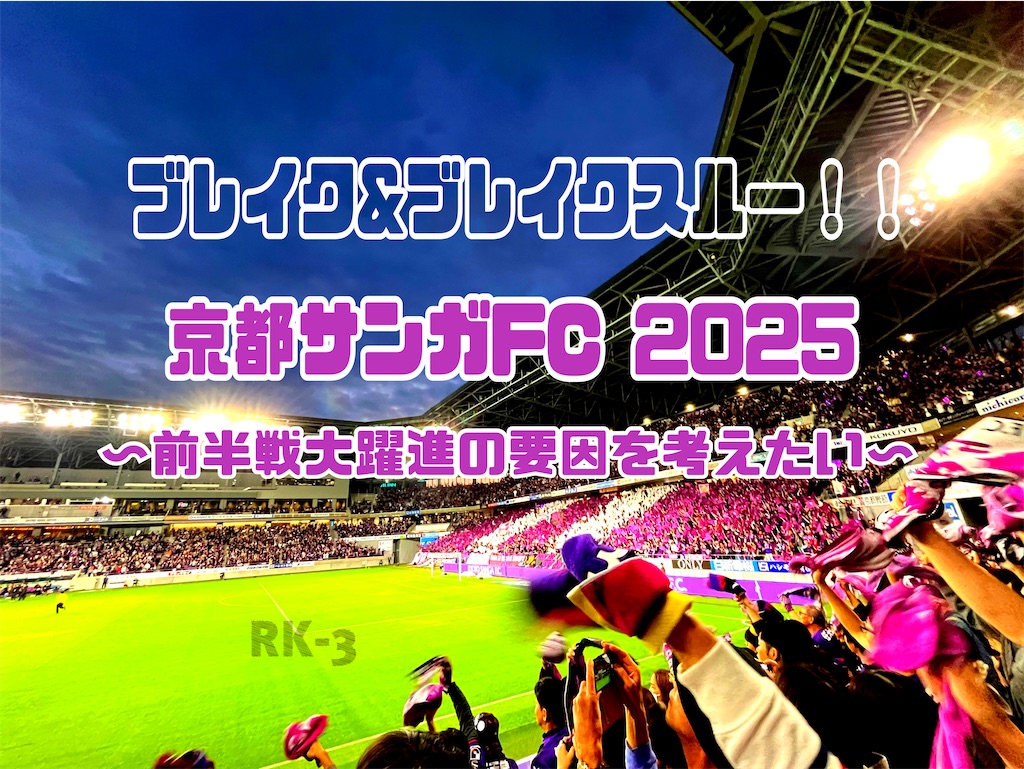
第10節、対戦相手はアルビレックス新潟。
2-1で逆転勝利を飾ったその試合の直後、どれだけ多くのサンガファンが順位表のページにアクセスした事でしょうか。
どれだけ多くのサンガファンがその瞬間を今か今かとリロードボタンを連打した事でしょうか。
そしてどれだけ多くのサンガファンが、そこに表示されたその画面をスクリーンショットで収めた事でしょうか。

京都サンガFC、大大大躍進!!!
2025明治安田J1リーグは6月1日の試合を以って前半戦最終戦となる第19節までを消化。ACLEやクラブW杯の兼ね合いもあって試合数に差はありますが、これを以って前半戦が終了した事になります。
…クラブ史上初めて自分達の前に誰もいない立場に立ったサンガの首位こそ長くは続きませんでしたが、リーグ自体が混戦かつ消化試合数が他クラブより多いという背景があるとはいえ、前半戦を2位という順位で終える事に成功。開幕3戦未勝利となった時は少し不安を抱く瞬間もありましたが、前半戦を終えてみれば20試合で10勝4分6敗の勝点34。今年のスローガンに《Brave & Breakthrough》を掲げたサンガですが、まさしくその言葉通りの躍進を見せたと言っていいでしょう。今まで見たことのない立ち位置、今まで見たことのない進撃……戸惑いさえ覚えるほどの日々に興奮せずにはいられません。去年の今頃を思うともう比較にもなんねえんだもん…。
もちろん、それこそ昨年のサンガが前半戦と後半戦でまるで別のチームになったように、その逆が起こって今の高揚感に比例するような順位で終われる保証はどこにもありません。しかしながら、例えば解説者の順位予想で近い位置にいた湘南や福岡が序盤戦で首位に立つなどリーグを席巻しながらも現在は下位に沈んでしまったその推移を見ると、20試合を終えた今の時点で2位という順位に立てている事は素直に評価されるべき事でしょう。
という訳で今回はそんな前半戦の躍進と健闘を祝する意味を込めて、2025年のサンガの躍進の要因、何が良くてこの順位で折り返せたのか?を考えていきたいと思います。
【ブレイブ&ブレイクスルー!!!京都サンガFC 2025、前半戦大躍進の要因を考えたい】
①"攻撃的守備"をカードとする守備組織の再考
②個性を増やした攻撃の明らかなバリエーション増加
③強度を担保する曺貴裁の悪魔的采配(後編)
④2024年後半を正しく引き継ぐ完璧な補強手腕(後編)
⑤そして、これから…(後編)
【クラブW杯観戦ガイド作りました!是非お使いくださいませ!】
↓
【Jリーグをもっと楽しめる(かもしれない)、2025Jリーグ開幕ガイド作りました!是非お使いくださいませ!】
↓
【オリジナルアルバム出してみました!聴いてみてくださいませ!】
↓
①"攻撃的守備"をカードとする「丸く大きく」の守備組織の再考
"曺貴裁京都"の特徴的なプレースタイルはこのクラブにとって極端なほど強みと弱みを表裏一体にしたようなスタイルで、端的に言えば2021年に昇格させて2023年までJ1に残した要因にして、2024年前半の不振に直結した要因でした。
極端なほどのハイプレス・ハイライン戦術は文字通り良くも悪くもというかある種のオールオアナッシング的な側面があり、それがあまり機能しなかった試合はカウンター以外の攻め手を作れず無理なプレスを剥がされ放題になって勝ち筋を失う一方、チームとしての戦術浸透は出来ていたのでハマった試合では確実に勝点を取れる。それが2023年は特に顕著だったんですが、2024年はいわば尖ったままでは相手の目も慣れて勝ち続けられないような状況に陥ったのがあの年の前半の低迷でした。この辺りの事は毎年ブログに書いていた事でもあるので、これ以前のことは是非過去のブログの方を参考にしていただくとして。
基本的に曺体制のサンガは良くも悪くもBoS理論に忠実なチームだと言えるでしょう。BoS理論とはすごーくざっくり言うと……サッカーは攻撃と守備の局面が分かれた競技ではなく、ボールを持っている時はゴールを奪う為の攻撃ができる、ボールを持っていない時はボールを奪う事そのものがゴールに繋がる攻撃になる=ボールを奪うという攻撃である…という考え方を根幹とした理論の話。
サンガは積極的なプレスとそこからのカウンター攻撃が特徴的なチームであるがゆえにメディア等でサンガが褒められる時には「攻守の切り替えに優れたチーム」みたいな表現をされる事が多かったように思いますが、正確に言えばサンガにとっては「ボールを奪う守備はそのまま攻撃になる」のであって、常に守備と攻撃は一つのセット…という戦い方を地で行くチームでした。つまるところ、サンガにとっては攻撃と守備は常に一体であり、90分そのものが一つの局面である…或いはサッカーを2つの局面にわかるとしたら、それは攻撃と守備ではなくアクチュアルプレーイングタイムとアウトオブプレーの2つになる…というサッカーをしてきたと。
言うなればこれはBoS理論に忠実なチームというよりは極端なBoS理論と評した方が適切かもしれません。ただJ2で勝ち抜く為には、11シーズンもJ2にいたチームがJ1で残る為には「尖った戦術を徹底してやり抜く」という事は割と重要な部分ですから、そういう戦い方に振り切った事は悪い判断だとは思わないですし、そしてそういう意識をチームに浸透させ、統一させた事は監督の手腕として見事だったと思います。
(中略)
ただ同時に、サンガは明確に「一つの戦い方しか出来ない」という状況にも明確に陥ってしまい、それが対戦相手との相性と試合開始10分の出来不出来が試合の全てを左右するようになっていきました。
前述した守備のスタンスもあるおかげで前線での守備には確かに強さがあったサンガなので、開始早々にハーフコートゲーム的な状況を作れてしまえば、そこから連続したプレスをかけやすくなって試合を優位に進める、そこで点を取り切り、1点を追う相手が前がかりになったところでオープンな展開に持ち込む…というのがサンガが勝つ時の大体のパターンでしたが、その序盤の陣取り合戦みたいな部分で敗れたり、プレス回避を得意とするような相手との試合だとその強みは一切無になってしまう……と。
【0-5からの逆襲】京都サンガFCは何が良くなったのか?真夏のV字回復のポイントを考察する回〜前編・ようやく手を付けたプレスのバランス調整〜 RK-3
サンガは得点の多くがカウンターだった事もあって「攻守の切り替えに優れたチーム」と目された事が多いが、これは湘南時代も含めた曺監督のチームの特色として、サンガは攻守の切り替えに優れているのではなく、いわば守備が攻撃に組み込まれているチームだ。それを最も簡単な言葉で表せば「攻守一体」という事になるのだが、サンガにとっての攻撃と守備はセットのようなもので、(中略) それを強みと捉える時、それを斜に構えて見ようとは思っていない。
ただサンガは極端なまでに攻守一体のチームだったからこそ、それが弱点になるケースも多かった。…ケースも多かった、ではない。極端な攻守一体はサンガの勝因と敗因を、そして長所と短所を一つに内包していた。
「攻守の切り替え」という言葉は…それが単に守備から攻撃への移行という意味であれば、攻守が一体化したサンガはそれをスムーズにやれていた訳で強みと言えるだろう。ただ、その言葉が攻守一体を意味するのではなく、あくまで"攻撃"と"守備"という異なるフェーズを行き来する時の切り替えを意味するのであれば、むしろそれはサンガができなかった部分であり、そして弱点ですらあった。詰まるところ、攻守一体を突き詰めた結果、サンガは攻撃の開始地点に何かしらの守備が無いと発車できないチームであり、守備とは全く別のフェースである"攻撃"を出来るチームではなかったように思う。前線でのアイデアやクオリティ不足を素人目でも感じる場面が多かったのはそれゆえだろう。
で、いつまでもあの試合の話を持ち出すのもどうかとは思いますが、やっぱりターニングポイントは昨年5月に0-5で敗れた広島戦だったんですよ。少なくとも曺監督はあの試合までは尖ったやり方に希望を持っていた。しかしあの試合でその希望は打ち砕かれた。あの広島戦で突きつけられたのは、未熟なスタイルを築こうとする過程での「できない」ではなく、これまでのスタイルが消費期限を切らした結果の「できない」であって、これまでの戦術に於ける曺貴裁京都のサイクルが一周してしまった事を突きつけた瞬間だったと思うんですね。
同時に、いずれにしても尖ったスタイルでJ1に上がったクラブがJ1に定着できるクラブになる為には、どこかで尖ったスタイルから…丸くなったとはよく言いますが、丸く大きな円に近づいていく必要がある。多くのクラブはそれを監督交代によって実現しようとしますが、元々の良さを残しながらそのフェーズに入るには現体制でやり切れた方がいいという側面もある。広島戦はその事に気付いた、或いはそこに踏み切れたタイミングになったんだとあの試合を解釈しています。
前置きが長くなりましたが、要は今季のサンガにとっての大きな要素は昨季後半の形をベースにするという意識を強く持てた事で、昨季後半の良い部分をしっかりと引き継げたところでした。その最たる例が守備陣のハイプレスとミドルプレスを使い分けるようなディフェンスで、基本的には鈴木義宜を司令塔にDFラインを揃えながら、初手からチャレンジするのではなく一度しっかりとブロックを組むところからスタートする。そこからハイプレスではなくミドルプレス気味に相手をサイドに追い詰めながら、対峙したSBがデュエルの状況に持ち込んだタイミングで中盤の選手がカバーする。これで安易に翻されるような場面は今季は昨季後半以上に激減。今季のサンガは落ち着いた状況にしてからサイドに追い込み、デュエルの構図を作って1対1が噛み合ったタイミングから中盤が加勢してハイプレス気味の守備を展開する…という連動がすごくうまくできている。特に「サイドに追い込んでデュエルの状況に持ち込む」という点では、そういうプレーを強みとする須貝英大の守備は福田心之助や佐藤響にも良い影響を与えていると思いますし。
ここで大事なのは、サンガはあくまでハイプレス・ハイラインを捨てたとかそういう訳ではないんですよね。例えば相手守備陣がGKを含めたビルドアップを始めた時はこれまでのように3トップから果敢にハイプレスをかけにいきますし、中盤での激しい攻防からショートカウンターに持ち込むようなプレーも残っている。要はこれまでハイプレス一辺倒だったところを一度守備陣の状況を落ち着かたところからスタートする事で、これまでの特徴だったハイプレスを「カード」として使えるようになった。これはこれまでの尖っていた部分を継続的な強みとする為に必要なバランス調整だったと思いますし、チームとして「チャレンジするべき場面」と「ステイするべき場面」を使い分けるタイミングをチームとして共有できていて、そのチーム全体がそのタイミングに呼応した動き方ができる。これは元々ハイプレス・ハイラインの意識の徹底に見られるように「チームとして意思を統一すること」はこれまでのサンガが培ってきたものですから、新しい戦術ではなくこれまでやってきたことの応用、第2段階として取り組めたことが大きく、何よりミッションを司令塔として完璧にこなした鈴木義宜には頭が上がらないです。
その上で曺監督にとっても、本人が元々どこかでフェーズ転換をしないといけないと思っていたのか広島戦でやらざるを得なくなったのかはわかりませんが、湘南時代のように毎年主軸が抜かれる状況ではそう簡単に移行できなかったでしょうし、曺監督としてもチーム作りに於ける初めてのフェーズに突入したんじゃないでしょうか。
②個性を増やした攻撃の明らかなバリエーション増加
これまでのサンガの攻撃パターンはワンパターンというか、厳密に言えば2パターンだったんですけど、要はバリエーションはかなり少なかったんですね。特に前線で起点を担えたピーター・ウタカがいなくなってからは顕著で、基本的にはハイプレスでのボール奪取からそのままショートカウンターをフィニッシュまで持ち込むパターン、或いは両SBを上げてクロスシチュエーションまでは持ち込み、エリア内でカオスを作り出すパターン。この辺りは山﨑凌吾や原大智のようにエリア内で高さを担保してくれる存在や、豊川雄太という少々の無理がある状況でもフィニッシュに持ち込める選手がいた事、チームとしての徹底はあったので勝ち筋に持ち込んだゲームでは威力を発揮しましたが、そうではないゲームになると一気に無力化してしまっていました。
結局のところ、結論は①と同じで昨季後半の良くなったところを引き継げたという話にはなってくるんですが……今季も攻撃の第一希望というか、最優先の選択肢はハイプレスからのショートカウンターで変わってないんですよ。そこの速さ、鋭さはやっぱり大切にしていくべき武器ですからね。ただ昨季後半からはショートカウンター第一優先としつつ、ショートカウンターが無理そうなら押し通さずにやり直す、ショートカウンターをキャンセルする…という事がチームとして出来るようになりました。
そこに関しては昨季後半からアンカーに福岡慎平というバランス調整が出来る選手が入り、中盤と3トップにそれぞれ平戸太貴とマルコ・トゥーリオというボールを持ってパスやアイデアで創造できるような選手が増えた。もちろん最初は速攻を試みるけれど、相手の帰陣が整ってしまったようなら一度彼らや福岡にまで戻して作り直す。そこから動き直す…その工夫が今季のサンガにはある。加えて今季はトゥーリオは怪我でプレータイムを作れていませんが、奥川雅也という質を担保できる選手も加わった事でチームとしてスピードに全振りしない選択をできるようになったんですね。ここはすごく大きかった。そういう幅の広がった今のサンガゆえ、山田楓喜もポジション争いは以前より厳しいですが彼が輝くスペースも以前より増えるんじゃないでしょうか。
加えて今季特筆すべきところは、平戸やトゥーリオ、武田将平のようなパサーや福田心之助のようなクロッサーがいる上で、必ずクロスボールに対してニアとファーに1人ずついる状況を作るという意識付けの徹底も素晴らしいのですが、個性豊かな攻撃陣のボールを引き出す動きの質と多彩さは今季の攻撃に彩を与えているように思います。
例えば一番わかりやすいのがエリアスと長沢駿の動きのタイプの違いなんですが、エリアスの場合はクロスやカウンター以外ではそこまで裏に抜ける…という感じではないんですよね。むしろ少し引いて待つ事により自分の前のスペースを作り、ファーストタッチでそこに持ち出す事でシュートの余裕と選択肢を作る。第7節広島戦や第9節鹿島戦辺りのゴールはそれがよく表れていたと思います。横への小さなスライドを挟む事でパスを受けた時の推進力を出せるようなイメージでしょうか。
一方、エリアスの負傷後に先発機会が増えて存在感を増す長沢は、少々展開が詰まった状況でも縦の動き、相手DFラインの背後へのアクションを何度も起こすんですね。それにより相手DFが長沢を無視できない、ケアできないような状況を作り相手DFを押し下げていく。もちろんそれで長沢に決定機が訪れるようなボールが入れば一番いいですし、長沢にボールが入らなくても長沢が縦の深みを作った事でシャドーのポジションで他の選手が使えるスペースが増える。ここにWGが入り込む、インサイドハーフの選手が入り込む事でチャンスに繋がる…と。CFの動きのタイプがこうも違うと、相手DFもそこの交代だけで対応を練り直さないといけない。そこにギャップを作りだす事もできる。エリアスと長沢の動き方の違いはそういうストライカーのタイプとしての面白さがよく表れていると思います。
決勝点の場面の平賀めちゃくちゃ素晴らしい。
— RK-3 (@blueblack_gblue) 2025年5月7日
一度コントロールがズレたところからボールを残したところもそうだし、あのプレーから間髪入れずに須貝とクロスするようにダッシュしたことで相手のDFを完全に引っ張り出した。ああいう粘りからの連続性はこのチームにとって大事なこと。
エリアスと長沢の対比は一例ですが、今期のサンガは多彩な顔触れのアタッカー陣がボールの貰い方にそれぞれ個性を持っていて、その上で全員が労を惜しまずそれをやる、体力の続く限りはそれを繰り返すという共通項を持てているんですよね。
同時に、福岡や武田は交通整理をしながら彼らがそういうアクションを起こせる時間を作り、平戸は彼らのムーブに応えるようなスルーパスを出せる。一方で川﨑颯太のようなタイプだと、例えば前述の長沢が空けたスペースに必ず走り込む事で努力を努力のまま終わらせない。中盤より後ろの選手もそういうアタッカー陣のそれぞれの個性を認識し、それに合わせた振る舞いをしてくれる。その連動が今季のサンガの強みと魅力であり、そして原-エリアス-トゥーリオの看板3トップが揃って離脱してもちゃんと勝ちを重ねられる土台となった。昨年後半の形を正しく引き継ぎ、ブラッシュアップしていく……その狙いは想像よりも上手くいっていると考えられます。
原-エリアス-マルコ
— RK-3 (@blueblack_gblue) 2025年6月12日
松田-長沢-奥川
平賀-ムリロ-山田
サンガちゃん3トップ3セット作れそうになっててビビる
【③強度を担保する曺貴裁の悪魔的采配④2024年後半を正しく引き継ぐ完璧な補強手腕⑤そして、これから】
ではでは(´∀`)