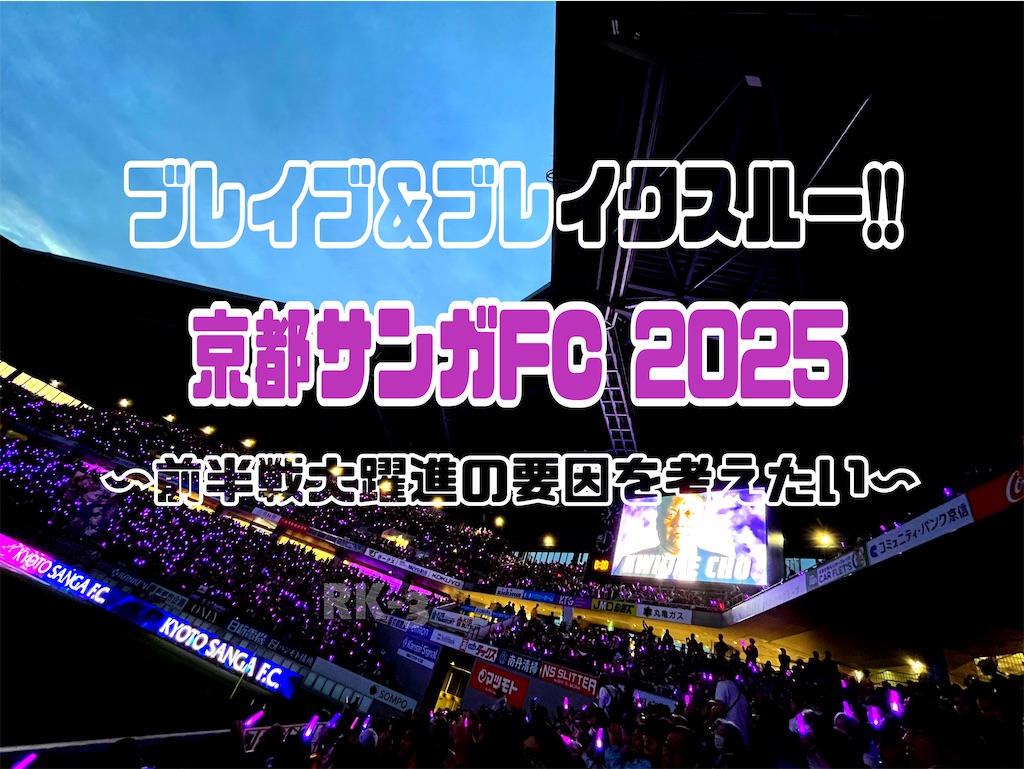
第10節、対戦相手はアルビレックス新潟。
2-1で逆転勝利を飾ったその試合の直後、どれだけ多くのサンガファンが順位表のページにアクセスした事でしょうか。
どれだけ多くのサンガファンがその瞬間を今か今かとリロードボタンを連打した事でしょうか。
そしてどれだけ多くのサンガファンが、そこに表示されたその画面をスクリーンショットで収めた事でしょうか。

京都サンガFC、大大大躍進!!!
2025明治安田J1リーグは6月1日の試合を以って前半戦最終戦となる第19節までを消化。ACLEやクラブW杯の兼ね合いもあって試合数に差はありますが、これを以って前半戦が終了した事になります。
…クラブ史上初めて自分達の前に誰もいない立場に立ったサンガの首位こそ長くは続きませんでしたが、リーグ自体が混戦かつ消化試合数が他クラブより多いという背景があるとはいえ、前半戦を2位という順位で終える事に成功。開幕3戦未勝利となった時は少し不安を抱く瞬間もありましたが、前半戦を終えてみれば20試合で10勝4分6敗の勝点34。今年のスローガンに《Brave & Breakthrough》を掲げたサンガですが、まさしくその言葉通りの躍進を見せたと言っていいでしょう。今まで見たことのない立ち位置、今まで見たことのない進撃……戸惑いさえ覚えるほどの日々に興奮せずにはいられません。去年の今頃を思うともう比較にもなんねえんだもん…。
もちろん、それこそ昨年のサンガが前半戦と後半戦でまるで別のチームになったように、その逆が起こって今の高揚感に比例するような順位で終われる保証はどこにもありません。しかしながら、例えば解説者の順位予想で近い位置にいた湘南や福岡が序盤戦で首位に立つなどリーグを席巻しながらも現在は下位に沈んでしまったその推移を見ると、20試合を終えた今の時点で2位という順位に立てている事は素直に評価されるべき事でしょう。
という訳で今回はそんな前半戦の躍進と健闘を祝する意味を込めて、2025年のサンガの躍進の要因、何が良くてこの順位で折り返せたのか?を考えていきたいと思います。
【ブレイブ&ブレイクスルー!!!京都サンガFC 2025、前半戦大躍進の要因を考えたい】
①"攻撃的守備"をカードとする守備組織の再考(前編)
②個性を増やした攻撃の明らかなバリエーション増加(前編)
③強度を担保する曺貴裁の悪魔的采配
④2024年後半を正しく引き継ぐ完璧な補強手腕
⑤そして、これから…
【クラブW杯観戦ガイド作りました!是非お使いくださいませ!】
↓
【Jリーグをもっと楽しめる(かもしれない)、2025Jリーグ開幕ガイド作りました!是非お使いくださいませ!】
↓
【オリジナルアルバム出してみました!聴いてみてくださいませ!】
↓
③強度を担保する曺貴裁の悪魔的采配
まあ、言ってしまえば今季のサンガの躍進って、①〜④で言ってることの根っこにあるものは実は全部同じだったりするのですけども、①で述べたような守備のバランス調整、②で述べたようなアタッカーの多様性は最終的にこの③に繋がってくるんですよ。
今季のサンガの大きな特徴として「後半の得点が多い」というところがあるんですね。今季のサンガの得点数は20試合を消化した時点で30点ですが、このうち21点が後半のゴール、それも更に17点が61分以降、即ちラスト30分での得点という事になります。今季で言えば第8節柏戦、第9節鹿島戦、第15節町田戦辺りの劇的ゴールが印象的ですが、それ以外にもラスト30分及び後半アディショナルタイムでの得点がチーム総得点の半分を数えている事になります。
昨年まで…厳密に言えば昨季前半までのサンガは前半勝負型のチームでした。
というのも、前述したようにこれまでのサンガは相手との噛み合わせが試合の勝ち筋をそのまんま左右するので、前半が良い試合は勝てる、前半が悪い試合は勝てない…と言った具合に前半の内容がそのまま勝点に直結していましたし、逆に前半から出力を全開にするがゆえに勝ち筋の試合の前半で取りきれなくてバテて散る…というのがよくあるパターンでした。しかし今季は前半はハイプレスを連続するのではなく、一度鈴木を中心にブロックを組んだところからカードとしてハイプレスを繰り出すやり方にシフトした事で大幅に省エネ化できたんですよね。まずここは一つ要因として大きいです。
一方、攻撃に際しては原大智へのロングボールへの対応、エリアスや長沢のアクションに対する調整、攻撃を仕切り直したタイミングでのプレスの修正で相手にアップダウンを強いるような攻撃ができている。今季のサンガはこれまでのような前半勝負スタイルというよりも、前半は当社比で消費エネルギーを大幅に削減しながら「如何に相手にストレスを与えるか」「如何に相手に負荷をかけるか」という戦い方をし、前半にその伏線を張るようになった…と。
その上で今季の重大なポイントはベンチメンバーの豊富さ。

今季の出場選手をざっとまとめるとこんな感じなんですけど、SBを3人で2つを回すとして鈴木義宜のところを除けば、全ポジションにレギュラーレベルの控え、或いは1番手か2番手かはっきりしなくとも問題のないレベルの選手が揃っていて、実質2チーム分組めるような勢いになっているんですよね。ましてやここに画像スペースの兼ね合いでムリロ・コスタと平賀大空記載できてないし、しかも山田楓喜まで復帰した訳で。ふうきふっき。やかましいわ。
原-エリアス-マルコ
— RK-3 (@blueblack_gblue) 2025年6月12日
松田-長沢-奥川
平賀-ムリロ-山田
サンガちゃん3トップ3セット作れそうになっててビビる
チームとして去年よりも出力を制限してプレーできるようになった事は重要ではあるんですけど、それでも両SBはハイラインをキープする戦術ですから前線に走る時や帰陣のスプリント、そうでなくともチャレンジできるタイミングの時に発揮する強度を考えると、どうしても消耗の大きいサッカーである事に違いはないんです。
だからこそ昨年までの対戦相手は「なるべくサンガを走らせて、バテさせて崩れさせる」というアプローチをするようになってきたんですが、今季のサンガはちょっとこっちのバッテリーが50%付近になってきたぐらいのタイミングで、例えば3トップそのまま交代みたいなやり方が成立するチームになっちゃったんですよ。すると相手はサンガのバッテリーが49%になったタイミングで仕掛けようとしていたのに、その作業で相手のバッテリーも60%くらいになっていたのに、一気にバッテリー残量100%の人間がフルスロットルで強度を出してくる。「選手交代で100%の選手を出せるのは相手も同じだろ」と言われればそうなんですけど、サンガのようなスタイルのチームはスタイルの強みとトレードオフのように「それを持続させられるかどうか」という問題に直面する中で、今季のサンガは強度を担保しながら殴り続ける事ができるという戦法を編み出してしまった。これは非常に大きなポイントです。
象徴的なゲームは第11節新潟戦、そして第15節町田戦でしょうか。共通点としてはどちらの試合も前半の出来はよくなく、事実としてビハインドで折り返した。しかし前者はハーフタイムの時点で福田と米本を下げて須貝と川﨑、そこから10分置きに松田→奥川、福岡→ペドロという校対策を敢行し、前半の内容は明らかに新潟でもロングボールや局地戦の激しさで消耗しつつあった新潟は途中から放り込まれた須貝、川﨑、奥川、ペドロの強度とクオリティに全くついていけなくなって、最後は自滅にも近い形で崩壊した。後者は前半に原を負傷退場で失う痛手こそ負ったものの、後半開始から米本と佐藤を下げて川﨑と長沢、そこからペドロ→武田、ムリロ→平賀を投入して同点弾に漕ぎ着け、フレッシュな選手への対応で更に消耗した町田に終盤のオープンな攻防を強いて決勝点に繋げた……町田戦の最後の得点なんかもう痺れましたもんね、なんでこの時間にカウンターであの人数上がれるんだよって。特にあのゴールシーンの平賀のスプリントは途中出場の選手にしか出来ない動きだったと思いますし。
ここで大事なのは今季のサンガの場合、交代はある程度最初から計画されたものだろういう事。もちろん試合や相手の状況によって変更する事もあるでしょうが、基本的に交代パターンは決まってるんですよ。SBは福田・須貝・佐藤のうち1人を余らせて、須貝が左右OKなので先発した2人や相手との状況に合わせてハーフタイムを目処に交代、中盤にしてもフル出場の確率が高いのは川﨑のみで、基本は福岡・平戸・米本・武田・ペドロを途中で入れ替える。前線も原とエリアスのどちらかを残して後は前述したメンバーを随時入れ替えていく…みたいな具合に。そういうシステムを今季は明確に築いているんですよね。もっともハーフタイム交代自体は曺監督は多いタイプでしたけど、今季はより「計画された交代」のニュアンスが強くなっているので、選手もモチベーションを失わずに身体をつくりやすくなっていると。
なので例えばスタートから出る選手には予めその旨を伝えておく事で力をセーブせずに出し切れる選手もいるでしょうし、一般的に選手が良くなかったイメージがつきがちなハーフタイムの選手交代にもネガティブなイメージを持たせないような前提をつくる。逆にベンチスタートの選手には「こいつをスタメンではなくあえてベンチに置く作戦だ」みたいな空気と流れを作ることでモチベーションを失わせない。
似たようなチームを挙げるなら、わかりやすい例がカタールW杯の森保ジャパンなんですよ。
当時、スペイン戦を終えた時に書いた試合考察ブログも読んで欲しいんですけど、ずっとチームが出せるトップクオリティで戦うというよりも、試合の時間帯に応じて出力セーブする、或いは一気にフルスロットルにする事で、試合のテンションを均一にするのではなく段差をつけていく。ずっと80%のサッカーをするだとか、無理に100%を出そうとして終盤に50%に落ちたりするのではなく、60%くらいの出力をベースに持ちながら100%を勝負所で出せる状況を作っていく…と。
もちろんその中でも細かい戦い方や相対的なサンガの立ち位置は異なりますが、W杯当時の森保監督は「先発で出るのか、中継ぎで出るのか、クローザー、ストッパー、リリーフで出るのか。役割の違いがあるだけで、チームが勝つために選手個々が機能していると思います」と明確なレギュラーの概念がない野球の継投に例えて交代策を説明していましたが、選手起用のスタンス、精神性は今季の曺貴裁監督にも同じことが言えると思います。実際にそのカードを切るタイミング然り、相手に与えるダメージ然り、こればっかりはもう「悪魔的采配」と呼びたい。なんなら畜生采配とすら呼びたい。その上で純粋に戦力値自体も上がりましたから、そのプランに食い込むための基準値も上がりましたし。
その循環を作ったのは紛れもなく曺貴裁監督であり、彼の特異なマネジメント能力の賜物でしょう。
例えば奥川。今季の奥川は基本的には途中出場がメインですが、あれだけの実力、実績、クオリティを持ち、結果も実際に出している選手としてそのポジションは不似合いではありますし、彼自身のパーソナリティは決してそういうものではないと思いますが…ちょっと腐るだとか、へそを曲げたりする事も不自然ではないと思うんですよ。それだけの選手がスーパーサブ的な扱いをされている訳で。しかし奥川はチームにエネルギーとクオリティーを試合途中から提供する働きを120%やってのける。これは任された場所でしっかりと仕事をしてみせる奥川のプロフェッショナルさもそうですが、前述したような目的を曺監督がしっかりと奥川のみならずベンチスタートの選手に説明する、その言葉を裏付けるようなスタメンとベンチがボーダーレス化したようなチームの雰囲気づくりを徹底するといった事を目に見える形で直に伝える、直に示す事で説得力を持たせている。その辺りのマネジメント力はやはり曺監督の面目躍如と言いますか、さすがの手腕だなと。サッカーがピッチ内と90分だけではないことの証明だなと改めて思わされます。
④2024年後半を正しく引き継ぐ完璧な補強手腕
とはいっても、前述のような交代策って結局のところ、どれだけ選手の意識や監督のマネジメントがあったとしてもそれに足る戦力が無いと実現できないものなんですよね。もちろん川﨑や福岡、福田や平賀のようにそれに足る選手を自分達で育てていく事は大事なんですが、それだけで成立させられるほどJ1リーグは甘くは無い訳です。
同時に今季の場合は、昨季後半のやり方をどう引き継いでいけるか、或いは前編で書いたように、尖ったやり方でJ1にしがみついたサンガをJ1に定着させる為には尖ったものを少し丸く、そして大きくする必要があった。その為に求められていたのが「やれることを増やす」「チームの幅を拡げる」という強化策でした。
一応私自身も、去年に「2025年の補強展望」的なブログを更新した際にこういう書き方をしていたんですよね。
サンガにとって予期せぬ大量流出でも起こらない限りは基本的には現在の編成がベースにはなります。一方で、チーム全体でどうこう…というよりも個人のスペックでチームパフォーマンスを担保しているポジションがいくつかあるのは事実です。
前提として、例えばそれゆえに「サンガは(曺監督)個人能力だけで勝ってる」との意見を持つ人もいますが、戦力を運用する事も手腕ですし、その為には一定のベースも必要なので、そういう単路的な斬り方には否定的な立場です。しかし「○○がいて成り立つ事」であり「○○がいない場合にプランAを成立させられる/プランBに移行できる」というような状況では決してないので、エリアスや原になってくるとスペシャルとしか言いようがないですが、チームの運用としてはプランAを継続できる存在、ないしはベースを維持しながらプランBに移行させられる存在が必要になってくるなと。
(中略) 曺監督が続投する場合の補強方針としては補強よりは現編成の維持が基本的には優先かなと。スタメンはある程度固まってはいるかなと思いますし。その上でチームとしてのブラッシュアップ、誰かがいなくても誰かが個人のタスク、チームの目的を引き継げるような編成を作る必要がある。一番簡単な言葉で言えば「選手層の底上げ」になるんですけど、単純に実力者を多く獲るというよりは、チームとしての幅を増やす為の戦力補強、そういう人材の獲得と現主力の維持が今オフのテーマでしょうか。
京都サンガFC 2024→2025 補強プラン展望〜後編・ポジション別補強優先度と今季の補強スタンス展望〜 - RK-3はきだめスタジオブログ
今季のサンガがやってくれた補強まさしくそれに当てはまるものだったと思います。上で引用した自分のプランで言えば、ちょうど「○○がいない場合にプランAを成立させられる/プランBに移行できる」という2つの状況の間に落ち着くような補強を実践してくれたなと。奥川に関しては経緯も含めてちょっと別枠としても、例えば前編で書いたように、長沢はエリアスの代わりはなれないけど、エリアスとは異なる解釈のプレーでチームのクオリティをキープしてくれる。ジョアン・ペドロもそうですし、現在は宮本がレギュラーですが対戦相手によってはウィリアムの方が適している試合もあって、そういう選択ができる状況にある。特に須貝の補強はその最たる例と言えるでしょう。彼の強さは福田や佐藤にはないもので、逆に須貝にはないものを福田や佐藤は持っている訳で。
彼らを組み合わせる事ができる状況を作った上で、前述したような曺監督の日頃のアプローチや選手起用が重なり、サンガはベースはベースとして持ち、強みは一本槍じゃなくてカードに転換した上で、自分達がやれる事を増やした、チームとしてやれる事の幅を拡げてくれた。獲得報道よりも先に準レギュラークラスがごそっと抜けた時は大丈夫かとも思いましたが、レギュラーはそのまま残したことも含めて大熊清GM、安藤淳強化部長がやりきった仕事ぶりは見事でした。
同時に……そもそも降格すると思われていなかったチームや町田のようなチームは別として、J1に昇格したチームの多くは大体特徴的なチームだと思うんです。そしてその殆どのチームが、尖ったところを丸く大きくしていくようなフェーズに入っていけない。それはなぜかと言えば、1年残留する度にキーマンがことごとく引き抜かれていくからなんですよね。例えば新潟であったり、鳥栖や大分であったり、曺監督が以前率いていた湘南なんかがわかりやすい例でしょう。そういうチームは積み上げではなく、毎年のように作り変えていかなければならない。だからチームとして、クラブとして大きくなるタイミングを作れないんです。
そう考えると、サンガはJ1に上がった時の立場は前述したようなチームと同じところにいるんですけど、それらのチームと大きく違うのは……これはちょっと当該クラブのファンの方が見ていて不快にさせてしまったら申し訳ないんですが、要は「もしうちが新潟や湘南だったら、少なくとも川﨑颯太はとっくに退団してる」という話で。サンガも毎年1〜2人程度は主力級が退団していますが、その程度に留まっている。海外移籍は抗えない部分がありますが、この立場のクラブとしては国内移籍をほとんど防げていると言っていいでしょう。だからこそ昨年のチームに穴埋めではない補強をする事が出来る。戦力は間違いなく22年より23年、23年より24年、そして24年より今年…となっています。
ここに関しては、やはり京セラをはじめとしたスポンサー陣のバックがある事を忘れてはならない訳ですよ。親会社がどこまでお金を出してくれるかどうかはクラブにもよりますし、実際京セラも若干渋かった時期はあるんですが、いずれにしてもJリーグクラブとして成立するだけの予算はしっかりとしたバックがついている事で大体確保できる。するとクラブとしては、クラブが稼いだお金をチーム存続の為ではなく戦力強化や慰留、クラブとしての施策に注いでいけるんですよね。補填や担保ではなく、ほぼそのまま上積みの為のプラスの投資に持っていける。これが親会社を持たないクラブとの大きな違いで、要は「チーム存続の為には選手を売却してキャッシュを確保しなければ生き残れないような逼迫性がない」という状況にはならない。サンガはこれまでそういうアドバンテージを若干浪費していたようなところがありましたが、今季はそのアドバンテージを正しく運用できているんじゃないかなと。
⑤そして、これから…
さあ、問題はこれが続くかどうかですよ。ここは恐怖のJリーグ、序盤戦を席巻した湘南や福岡が順位を落としていった中で、サンガがそうならない保証はどこにもない。さすがにここから残留争いに巻き込まれる事は想像しにくいですが、例えば2013年の大宮なんかは後半戦で8連敗を2回もやらかしたように、そういう事態に陥る可能性は否定できない。おそらく、有識者に後半戦の順位予想をやらせたら「サンガが最後まで持つかどうか」は一つの論点になるでしょうし。それこそ去年の町田じゃないですけど。
サンガがよく指摘されるのは「この運動量のチームだと夏場に落ちる」という懸念なんですが、個人的にそこはあんまり心配してないんですよね。
むしろサンガって夏の方が強いんですよ。2023年も2024年もそう。2022年は例外でしたがこの年は4月までが調子良くて5月から満遍なく負けていったようなシーズンでしたし。ここからのシーズンは飲水タイムがあるじゃないですか。サンガの欠点は積極性は保ちながらも時間経過と共に統率が緩んでポジショニングがバグってしまう事でしたから、要は前半と後半に一度ずつブレイクを挟める夏季はむしろチームのネジを締め直す時間を設ける事ができるので、そこで強度と統率を維持できるようになるんですね。そうなると逆に言えば、怖いのは9月中旬〜10月前半頃。残暑に加えてシーズン蓄積疲労が募った中で飲水タイムがなくなる事で、ネジを締め直すタイミングを失ってしまう恐れがある。個人的にサンガの7〜8月はそんなに不安には思っていませんが、それだけに9月以降がキモでしょう。
その上でここまで散々「チームとしてやれることが増えた」「2チーム分の選手を持てた」と語っていますが、唯一ここだけは個人の特性に依存しきっている部分が鈴木義宜の部分なんですよね。実際、鈴木が終盤からの出場となった町田戦は不安なシーンも少なからずあった。鈴木がもし離脱となれば相当苦しいかもしれない…という懸念はある。かといって宮本やウィリアムには鈴木の代わりよりも今季ここまで彼らが見せているような仕事に注力させたいですし、それはアピアタウィアも同じでしょう。個人的な希望としては、鈴木のようなリーダーシップ、DFリーダーとしての才覚を麻田将吾であったり、若手が担えるようになってほしい。そうすればこの前半戦は循環させられるのでは…と。
未来なんて誰にもわかりません。残り18試合、サンガは全勝するかもしれない。或いは全敗するかもしれない。可能性の話の結末は12月になるまでわからない……現時点での歩みがシーズンの総括を保証してくれるものではないですし、ここから後味の悪い成績に陥るチームもいくつもあった。ここまでの道のりにサンガは慢心も満足もしてはいけない。それは確かです。
しかしサンガが暫定ながら首位に立った新潟戦の後、曺監督はこういう言葉を残していました。
やっぱりこの時点で首位にいるのは全然満足するものではないし、何か自分たちが達成したことではないですけど、自分たちが歩いてきた道のりは間違ってなかったと肯定できるものであると思うので、そこに甘んじないで、また険しい道を自分たちで進めるように選手と一緒にやっていきたいと思います。
ここから先、いつの間にかサンガが中位に落ちてしまう事もあるかもしれません。勝負事は努力だけで夢は叶わない。仮にJ1の20チーム全てが世界最高の20チームで100%のクオリティを出したとしても優勝できるのは1チームだけで、3チームは降格する。相対的な順位づけがされるフィールドの上では、自分達の努力が全てを肯定してくれる訳ではありません。
だからこそ、今この場所にいるという事…少なともそれはこれまでの20試合を、20試合でやってきた自分達の努力を肯定してくれる何よりの証であり、意味がある。その意味を一つずつ食べてクラブは丸く、大きくなっていく。そして「常勝」と呼ばれるようなクラブを作る為には、2025年を天の気まぐれではなく千年の都のような時代の一歩目とするには、肯定された自信と掴んだ意味を結果に変えないといけない。この20試合で掴んだ自信と意味、ここからのサンガはそれを結果に変えていく為の戦いになります。
昨年、私はブログで「曺貴裁京都のサイクルは広島戦で一度終わった」と書いた一方で、「そこから2週目のサイクルが、曺貴裁京都の第二形態あるのなら、それを見てみたいとも思う」と書きました。サッカークラブにとって、プラスのターニングポイントは誰しもが得られる岐路ではない。この年を思い出ではなく分岐点とする為の冒険の本番はここから先の舞台です。
《①"攻撃的守備"をカードとする守備組織の再考②個性を増やした攻撃の明らかなバリエーション増加から読む》
ではでは(´∀`)