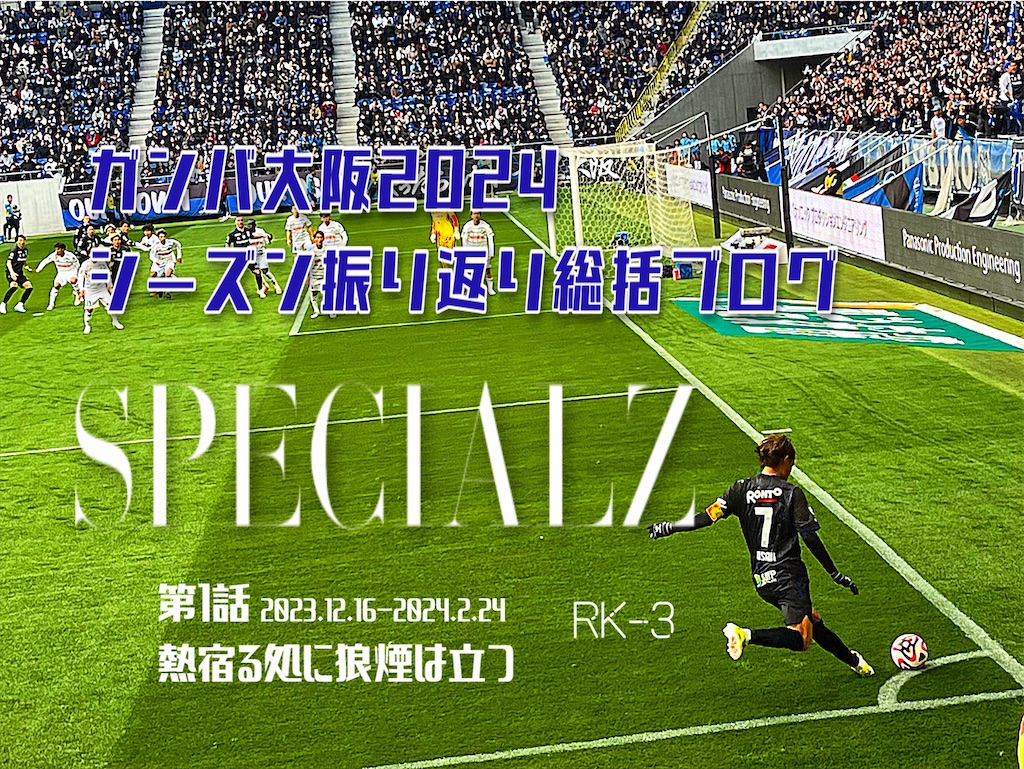
「残留争いに勝って喜ばせてしまうくらいなら、優勝争いに負けて悔しがらせてあげたい……」
2022年11月5日、カシマスタジアム。
その年の最終節にてガンバは鹿島戦を0-0で引き分け、どうにかJ1残留を果たした。引き分けという最低限のミッションは達成しながらも、それは他力。他会場の試合結果がスタジアムに入り、歓喜するゴール裏。その光景を見た宇佐美貴史が語ったのが冒頭の言葉である。
宇佐美や倉田、東口といった選手は、少し前の強いガンバに見を投じていた選手達だ。例えば2015年、チャンピオンシップという舞台で見た準優勝という結末に嘆息が包んだゴール裏の記憶と、15位という順位に歓喜の声を上げるゴール裏の現在…記憶と現在が生んだそのギャップは、自分達の立場がこうも変わってしまった現実を突きつけるのにこれ以上ない光景だったのかもしれない。
「強いガンバを取り戻す」──最初にそのフレーズを使ったのは、そういえば誰がいつの事だったのだろうか。いつしかその言葉は、復活を目指してもがき、あがこうとするガンバにとって、言ってしまえば呪いですらあったのかもしれない。
確かに過去のガンバは面白く、美しく、そして強かった。しかし当時とは時代が違えばトレンドも異なり、選手だって当然に違う。「機械的に…」とはよく言うけれど機械ですらアップデートを繰り返すのだ。それが人間が監督し、人間が動くスポーツに再現なんて存在する訳もない。時計の針が戻らない事と同じように、いくら「強いガンバを取り戻す」と呪文のように唱えたところで、未来というものは過去には存在しないのだ。過去の上に現在を重ね、現在の上に未来が乗る。過去を取り戻すのではなく、新しい強さを積み重ねていく事でしかガンバ大阪は復活できない。ここ何年かの苦悩の季節は、ずっと戦いようのない幻影に抗おうとしていた日々だったようにも思う。
2024年11月23日、国立競技場。
2年前には15位という現実に歓声が木霊したスタンドを、準優勝という躍進からきた嘆息が包む。
国立競技場で見せつけられたヴィッセル神戸の歓喜、スコアボードに刻まれた0-1の数字……。それは確かに強烈に悔しかったが、時間が過ぎ、帰路につくその時、喉元に残した後味は2022年の歓喜より遥かに心地良いものだった。
「残留争いに勝って喜ばせてしまうよりは、優勝争いに負けて悔しがらせてあげた方が良い…」
— RK-3 (@blueblack_gblue) 2024年11月23日
2022年に鹿島で残留を決めて歓喜するスタンドを見た宇佐美貴史が語った言葉がそれでした。
誇らしく讃えられるべき軌跡に一発回答で応えてくれない。それが決勝戦というもの。… pic.twitter.com/xpAVbYPyzy
強いガンバを過去に求めても過去には戻れない。取り戻せる過去はない。その時代のトレンド、その時代にいた人間にしか作れない。それがあの時取り戻せるはずもないのに追いかけた過去だった。
だが、過去の上に現在を重ねて未来を作る事はできる。その時に過去の記憶は礎として土台となり、その上に今の知見を乗せ、いつの日かその産物を人は過去と呼ぶ。そう考えれば、過去の栄えた時代も、今年ガンバがつくった「新しい繁栄」も、長い歴史の中で見ればそれぞれのスペシャルなんだと思う。それを人間という再現性のないスペシャルな個性が編み上げ、強さに程度の差はあれども、今にしか作れない特別なチームを紡いでいくのだ。
「今までのガンバの歴史の中でも、どのチームとも違う顔を僕らは持っている」
今回からは、2024年のガンバ大阪を総括して振り返るブログを4回に渡って更新していこうと思う。
最後まで是非、お付き合い願いたい。
【SPECIALZ 〜ガンバ大阪 2024シーズン振り返り総括ブログ〜】
第1話 熱宿る処に狼煙は立つ (2023.12.16〜2024.2.24)
第2話 ポヤトスガンバ・バージョン2.0 (2024.3.2-6.30)
第4話 "U" R OUR SPECIAL (2024.10.5〜12.8)
【過去のガンバ大阪 シーズン振り返り総括ブログ】
【2024年のJリーグを振り返る記事も色々更新しています。それらの記事はこちらにまとめておりますので是非!】
↓
【オリジナルアルバム出してみました!聴いてみてくださいませ。】
↓
万博記念公園駅を降り、モノレールに沿うようにしてそのまま東側へと直進していくと、EXPO CITYの駐車場と交差する歩道橋へと辿り着く。
駅を降りてからパナスタに向かうまでは2つのルートがあり、どちらのルートで向かうかは割と気分次第で決めているのだが、前述の東側を直進するルートを進むと、否が応でも過去と現在の境に立たされたような気分になる場所がある。

道順なんて把握しているから、普段は気付くことも気にすることもなかった。そもそも、人が通ればただの標識として隠れてしまうだけの存在感だろう。
実際にこれまでは気付いてすらもいなかったこの表示に初めて気を取られたのは2023年12月16日の出来事だった。いま考えれば、この日この標識をとらえたこと自体がこの日が終わった時の感情を匂わせるものになったような気がする。虫の知らせとも少し違うが、第六感が敏感にでもなったのか……。
この日、私は橋本英郎の引退試合を観るためにパナスタへと足を運んでいた。
引退試合の多くは「ガンバ大阪選抜」となるのがベターではある。しかしこの時は橋本英郎本人の強い意向により、ガンバ選抜ではなく2005年チームの再現という形式でこの試合は行われた。後半開始前、橋本英郎が、遠藤保仁が、宮本恒靖が、シジクレイが、山口智が、フェルナンジーニョ、二川孝広、大黒将志、そしてアラウージョ……あの日、このクラブにとって最も美しい瞬間を奏でた面々が18年ぶりにピッチに集まり、円陣を成す。
彼らが揃う姿が構えたカメラのフレームに収まった時、多分自分は少し泣いていた。その45分間はあまりにも美しく、あまりにも眩く、この上なく幸せな時間だった。何から何までもがあの日の…私がサッカーを見始めて、ガンバ大阪というクラブに魅せられた18年前と同じ姿……帰り道に太陽の塔を眺めた時、クレヨンしんちゃんオトナ帝国で20世紀博に行った時のひろしってこんな感じだったのだろうかとさえ思った。自分もどこか、歳をとる感覚というものを覚えたような気がする。
だが、そんな幸せな時間の跳ね返りはじわじわと押し寄せ、大阪モノレールを降り、人並みもまばらになった乗り換えのホームで急に喪失感として襲いかかってくる。「強いガンバを取り戻す」……近年何度も聞いたセリフがリフレインするように脳裏に響くが、橋本英郎の引退試合で見た幸せな時間は少し間を置き、ガンバが帰ろうとする場所は結局、あの監督とあのメンバーでしか成しえない奇跡の時代だったという事を突きつけ、一気に夢から現実に引き戻される感覚に苛まれた。それはまるで2005年メンバーの躍動が今のガンバ大阪に過去を過去として受け入れる事を迫るかのようで、過去は帰る場所にはならない…人智が抗えない定めを、他でもない過去の英雄が誇示してきたのかように。
だが少なくとも、2023年のガンバはこれまでガンバを蝕んできた「取り戻す」という言葉からの訣別を目指していたようにも感じる。ダニエル・ポヤトスというこれまでのガンバの歴史とは異質な人材を招聘した。7番を遠藤保仁から宇佐美貴史へと継承し、ユニフォームをアンブロからヒュンメルへと変更した。宇佐美は背番号変更について「アンブロの7番の歴史をヤットさんが作った。自分はヒュンメルの7番の歴史をつくる」と語っていた。これらは全て、あくまでそれぞれの個別の事例ではある。偶然タイミングが重なったという事に過ぎない。だが、ポヤトスというこれまでのガンバの文脈と異なるタイプの監督就任と時を同じくして、不可侵にも見えたものが継承を遂げた事自体が、過去との訣別というよりも過去に未来を求める事と訣別したようにも見えた気がした。
今振り返れば2022年は未練を断ち切る事と引き換えに過去の貯金を使い切って残留まで辿り着いた一年であり、2023年は思い出が纏う皮表を脱ぎ捨てる為の一年だったのかもしれない。産みの苦しみというよりも脱皮する為の一年と評する方が近いように感じる。
そして未練を振り払って取り組んだ新しいサッカーを目指した2023年というシーズンは真っ暗闇ともまた違う、一筋の光は差し込んでいる窮屈な山道を息を詰まらせながら進むような旅路だった。今自分達が進んでいる道、それ自体はきっと正しい。だから選手達は結果が出ない中でも、少なくともポヤトスと共に志した道を歩み、トライし続けた。だがこの道そのものが正しい出口に繋がっているのかどうかはわからない。一筋の光に辿り着いた先が正しいゴールなのかがわからない……2023年終盤に見た鬱屈とした感覚は、同じ方向を向いているからこその疑心暗鬼が根底にあったように思う。
ただそれでも、チームとして同じゴールを目指そうとした跡は2023年の時点で伝わっていた。だからこそクラブはポヤトス続投という一つの勝負に出るような決断を下せたはずだ。そうなれば今年やるべき事は一つしかない。
歴史的なセールスを達成し、長年に渡って精力的な活動を続けるとあるロックバンドのリーダーは「俺がリーダーとしてやった仕事は"バンドとしてどの山を登るか"を明確にした事だ」と語った。少なくとも2023年のガンバはポヤトスをリーダーとしてそれはやった。であれば、次は去年曲がりなりにも「こういう方向性でいきたい」と定めて提示したスタイルを、強化部が、監督が、そして選手自身が正解に近づけていく事。山に辿り着く為の道をしっかりと歩く事と、その為の努力が求められる。2024年というシーズンはその前提の上に立っていた。
新たにフットボール本部を設置するなど強化体制を刷新して挑んだ移籍市場。挨拶代わりの補強情報はシーズン閉幕を待たずに、なんならフットボール本部設置の発表より先にもたらされた。確かにCB獲得の必要性は誰もが認識していただろうが、その対象がまさか中谷進之介になるとはさすがに予想した人は少なかっただろう。Jリーグ全体でも弩級の補強からガンバの2024年は幕を開ける事となる。
比較的出入りが少ないシーズンの方が多かったガンバにとっては2022→2023年の移籍動向ですらメンバーが入れ替わった印象を持たせたが、今年はその比ではなかった。藤春廣輝は出場機会の激減に端を発し、クォン・ギョンウォンや鈴木武蔵も稼働率と年俸を踏まえればある程度予想の範疇であったとしても、山本悠樹、髙尾瑠、佐藤瑶大といった面々が一気に抜けた事…特にあくまで準レギュラーだった髙尾や佐藤とは異なり、山本の退団、それも国内クラブへの移籍には大きなショックがあった。キーマンの役割を託されていた選手が、例えば前年の昌子源のように元々鹿島の選手だとかそういう背景のないクラブに引き抜かれたという事実は「このまま低迷が続くようならガンバは獲るクラブから獲られるクラブになってしまう」という危機感を抱かせるには十分すぎる出来事だったと思う。
ただ山本を除けばスカッドのコアとなる選手は残した上での選手入れ替えを断行したガンバは、ガンバの歴史の中でも屈指とも言える大型補強をここから見せつけていく。前述の中谷というクラブ史に残るディールを皮切りに徳島時代にポヤトス監督と仕事を共にした岸本武流と鈴木徳真、複数クラブとの争奪戦になっていたとも言われる山下諒也、そして柏のキーマンとして存在感を誇っていた山田康太、極め付けは多額の移籍金を投じてウェルトン…一森や坂本といった復帰組やルーキーを除いても8人もの選手を迎え入れ、チームの1/3ほどをごそっと入れ替えた事は衝撃的なオフだったと表現する他ない。しかしながら、どちらかといえば補強には保守的な傾向があったガンバがこれだけの動きを見せた事は、昨年の補強も含めてだがクラブとして変わろうとしている印象を強く抱かせ、そしてその人選が決して補充ではなく補強としての人選だった事は言わずとも伝わる顔触れだったと言えよう。期待された選手が期待通りに働くかどうか、それはシーズンを迎えてみないとわからない。それでもクラブは賽を振った。その意気は十分に伝わるオフだったと思う。
極め付けはレジェンド…レジェンドという表現が物足りなく感じるほどの存在、遠藤保仁が帰還する。
過去は過去として取り戻せない。ガンバはその未練を断ち切る為の2年間を過ごした事は先にも書いた通りだ。しかし過去を知る者は今に知見をもたらす事ができる。過去は未練を断ち切り、史料として積み重ねていくものだ。ましてや、理想像にグアルディオラよりもヨハン・クライフの名を挙げる事が多いポヤトス監督と、かつてクライフに師事したカルロス・レシャックから受けたたった半年の指導を今でも一番の影響として語る遠藤保仁は理想とする場所も似通っているはずだ。影響力の強い人物をコーチに置く事への不安感を表す人もいたし、その懸念はわからなくもない。だがプレーヤーとしての経験に乏しいポヤトス監督にとって、トップ選手としての目線を持ちながらスタッフ陣との間に入り、かつ自身と近いサッカー感を持つ遠藤保仁という存在は、言語とはまた別のところでの双方向的な通訳としてこれ以上ない人材だったんじゃないかとも思う。遠藤保仁という唯一無二の存在ゆえ、その招聘は必ずしもポヤトスの為の招聘という訳ではないだろうが、ポヤトスに為にならない招聘でも無かったはずだ。
「もうちょっと出来ていなかったところを埋められれば、去年より絶対いいキャプテンになる」との決意をポヤトス監督にも伝えた宇佐美が主将を続投し、山本とクォン・ギョンウォンの退団で空席となった副将の席には新加入の中谷と来日5シーズン目のファン・アラーノが就いた。
「(副キャプテンの2人と)俺と3人でもっとチームのコミュニケーションの機会をぐちゃぐちゃにして、人種、年齢、仲の良さを問わずもっとかき乱してやるべきだった」「俺が(山本)悠樹とかディエゴ(クォン・ギョンウォン)を信頼して(責任を)渡せていたら、もっとできたと思う感覚があった」事を昨季の反省点として挙げた宇佐美は福岡将太や三浦弦太などのコミュニケーション能力に長けた選手に「アップとか、食事とか全部同じグループで固まらないようにちょっと活性化させてほしい」と頼むなどの工夫を散りばめたが、そういう「去年できなかったこと」を今年できるようにする過程の中で、元来リーダーシップとしての性質を持ち、若手からベテランまで分け隔てなく絡み、英語まで使えてしまうコミュ力お化けの中谷の存在はチーム運営の相方としてこれ以上ない相棒だった事だろう。アラーノも外国籍選手の意見を汲み取りながら、それをしっかりと日本人選手と繋げ、融合させる潤滑油となった。主将のポストを任されずとも東口順昭や倉田秋のように宇佐美より年上で主将の逃げ場となれるような存在がいて、福岡や三浦のような3枚目も担えるムードメーカー、そして復帰した一森純のように声でチームに影響を与えられる選手がいる。
「熱量」──宇佐美を筆頭に、今季のガンバの選手へのインタビューで何度も聞く事になるその言葉と共に、2024年のガンバは歩み始めた。
宇佐美が「全ての窓が開いて風が入ってきた感じ」と表現したように、去年は同じ場所を目指しながら鬱屈してしまったような空気感を振り払い、間違っていないはずのこの道を邁進できるだけの熱量を体現できるメンバー、キャラクターは揃った。

2月24日、開幕戦は敵地でのFC町田ゼルビア戦となった。
町田は昇格組だがその補強ぶりと選手層を昇格組と捉えるには無理があり、何より今のガンバとの相性が良くないプレースタイルのチームである。それでも決意のシーズンの開幕戦には、去年と違う青黒の姿を見せなければならない。
前半は町田に呑まれるかのように鬱屈した試合展開に陥ってしまった。守備陣の奮闘こそあったが、それが攻撃に結びつかない。それはまるで去年の轍を辿っているようですらあった。しかし──。
🎥ゴール動画
— ガンバ大阪オフィシャル (@GAMBA_OFFICIAL) 2024年2月24日
🏆2024明治安田J1リーグ 第1節
🆚FC町田ゼルビア
⌚84分
⚽ #宇佐美貴史
見逃し配信は▶️@DAZN_JPN
登録は▶️https://t.co/cmHuKWaYRL#ガンバ大阪 #GAMBAOSAKA pic.twitter.com/cDyTSDRBfb
「全ての窓が開いて風が入ってきた感じ」
野津田の山中に燻る不安感を、最後の仕上げとして春一番のように吹き飛ばしていったのは背番号7の右脚だった。
窓から吹き込む風が内側からドアを叩き、この扉をこじ開ける。ガンバの2024年がここから幕を開ける。
【SPECIALZ 〜ガンバ大阪 2024シーズン振り返り総括ブログ〜】
第1話 熱宿る処に狼煙は立つ
第2話 ポヤトスガンバ・バージョン2.0
第3話 魘されて…夏
【過去のガンバ大阪 シーズン振り返り総括ブログ】